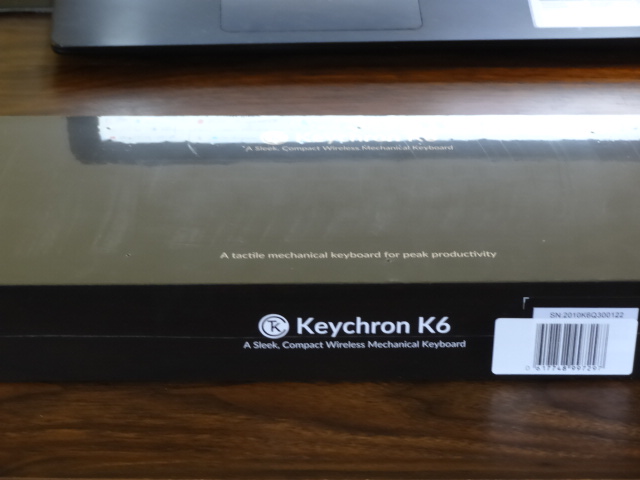某SNSで日本人は意地悪、という投稿が流れてきました。
それはニュース記事の紹介で、僕はその記事は読まなかったのでどういう文脈かはわかりませんが(読まなかったんかい)、僕も日本人は意地悪だなと思う事があります。
「日本人が」というより、僕が他人に対して意地悪だなぁと思うことが多いのです。
そしてそれは日本人的な考えなのかな、と思うのです。
カナダでは「個人それぞれ事情がある」というのを尊重される傾向にあります。
たとえば給食で全員が同じものを絶対に食べなければいけない、というようなことがありません。一人一人好みが違うのはもちろん、アレルギーの有無、体格、食べられる量、宗教、食事療法(ベジタリアンとか)も違うのは当たり前ですよね。
でも…。
現地の日本食レストランでアルバイトしていたときも、好き嫌いがある人の多い事といったら!
サビぬきとかガリなしなんてレベルじゃなくて、セットメニューから一部の材料を変えろとか(マグロの代わりにサーモンくれとか)、この醤油じゃなくてあの醤油はないのか、やりたい放題(別の醤油なんてありません)。
アレルギーを持つ人も多く、甲殻類アレルギーの人なんて寿司屋にはそもそも来なければいいのにと思うことも。だって甲殻類を調理したまな板の物は食べられないなんて言うんだもん。
そしてこのご時世で、マスク着用が義務になったり、バスの運行時刻が変更になったり、店の営業時間が変更になったりと、いろいろ変更がありますが、そのたびに、SNSは個人の主張で荒れます。
「私は肌のアレルギーでマスクが出来ないのに!」とか、「病院に行くのにバスが必要なのに!」とか。
ユーザー同士で口論になるぐらい荒れていても、そんな個人的な都合については叩かれていないように見えます。
職場でも、
- 仕事の覚え方や覚える速度は人それぞれ、
- 子供の発熱や親の介護など家庭の事情も人それぞれ、
なんて言って、仕事の覚えが悪くても、家庭の事情で早退や欠勤になっても、人それぞれ事情があるんだからしょうがないでしょ、という空気感です。
それで従業員にしわ寄せが来ても、社員同士で愚痴を言う時の矛先は従業員じゃなくて、社員に穴埋めをさせてくる上司や会社です。
でも、僕個人としては、なんか大げさに聞こえるんですよね。
甲殻類アレルギーなんて自分の周りには1人もいないし、なのに小さな日本食レストランに毎日のように甲殻類アレルギーのお客さんが現れるのも変だし、清潔にしているとはいえエビを調理したまな板で刺身も作るのに店内でアレルギー反応が出た人もいなかったし、そもそも注文前に念を押すような人が寿司や刺身がメインの店に来てる事自体不自然。
言っちゃいけないことだけど、アレルギーじゃなくて単なる好き嫌いじゃないの?と言いたくなるくらい。
マスク着用の件だって「じゃあ外出は控えて下さい」とか、バスの件も「運転できる友人に頼んだりタクシーを利用すれば?」と思ってしまいます。
仕事だって、同じ役職なのに「私は覚えが悪いから」なんて3年も言い続けて仕事の量が違うのは納得が良いかないし、子供もいなければカナダ国内に親類がいない自分は家庭の事情で遅刻早退欠勤をすることもないのでなんだかなーと思います。
でもこういう考えって意地悪ですよね。なんだかそんな意地悪に思ってしまう自分が、日本人っぽいんだなぁと思います。
(そうじゃない日本人も多いんでしょうけど)
ま、レストランのアルバイトは20年前の話だし、マスクやバスに文句を言っている人はSNSの中だけで知り合いにはいないし、仕事は在宅になってから作業量がガラっと変わって何一つ困ってることはないんですけどね。
本来みんなで守ると決まっていることなのに誰かが“個人の都合”で免除されているのを見ると、「そんなの知らん、ルールは守れ」と意地悪な気持ちになってしまいます。
ちなみに1人1人違う個人の事情に合わせるようなことを、英語では accommodate (アコモデート)と言います。
ベジタリアンなので職場のポットラックに参加できません、と上司に言ったことがありましたが(自分も個人の都合で免除してもらってるw)、
We can accommodate
(それなんとかできますよ)
と言われました。
なんとかできるって言われても参加者に肉料理を遠慮してもらうのも誰かの肉料理を避けるのも嫌なので改めてお断りしましたが。
嗚呼、やっぱり意地悪w
Photo by pixabay.com